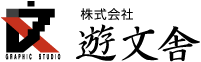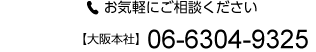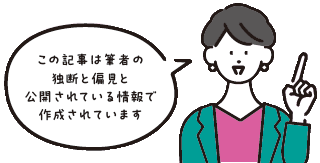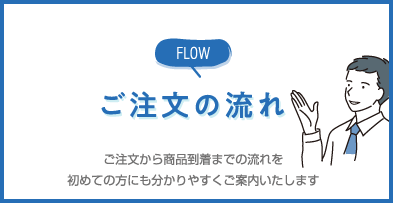AIと話してみたら、性格もクセもぜんぜん違った件

ChatGPT(OpenAI)/チャットGPT(オープンAI)
| 運営企業 | OpenAI(アメリカ) |
|---|---|
| 学習材料 | 書籍、Web記事、コード、ユーザーとの対話履歴 (※設定次第) |
| 特徴 | 知識量が豊富で、論理的な説明が得意。 雑談もこなす万能型。 |
| 個性 | 真面目で優しい。たまに冗談がスベる、根は誠実。 日々の進化が目覚ましくGPT-5の登場も。 |
| 注意点 | 入力内容が学習に使われる可能性あり。 設定でオフにできる。 |
| 使い所 | 意外とログインしなくても使えます。 まず身近な疑問なんかを聞いてみるなどお試しにはちょうど良いです。 |

Gemini(Google)/ジェミニ(グーグル)
| 運営企業 | Google(アメリカ) |
|---|---|
| 学習材料 | 検索データ、GitHub、YouTube、Google製品の利用情報など |
| 特徴 | 検索連携が強く、最新情報に強い。 画像や動画も扱える。 |
| 個性 | 情報通でスマート。ちょっと冷静すぎて距離を感じることも。検索結果を行頭で終わらせるのはサイト運営者の泣き所。 |
| 注意点 | Googleアカウントと連携する場合、個人データの扱いに注意。 |
| 使い所 | Googleアカウントにログインした状態でGoogle検索を使うと検索結果の要約を行頭に表示してくれます(設定でオン・オフ可能)。これが便利すぎる。要約には信頼性の高い情報が利用されているそうですが裏取りは大事です。 |

Copilot(Microsoft)/コパイロット(マイクロソフト)
| 運営企業 | Microsoft(アメリカ) |
|---|---|
| 学習材料 | Bing検索、Office製品、GitHubなど |
| 特徴 | Office連携が強く、作業支援に特化。 文章・表・コードも得意。 |
| 個性 | 仕事ができる相棒。ちょっとおしゃべり好き。 マスコットはイルカじゃなくてキノコ。 |
| 注意点 | Microsoftアカウントと連携する場合、データ共有範囲を確認。 |
| 使い所 | Windowsマシンに住んでいるAIなのでWindows利用者には一番親しみやすい。 ヘルプの代わりにもなるのが◎ |

Grok(xAI)/グロック(xAI)
| 運営企業 | xAI(アメリカ) |
|---|---|
| 学習材料 | X(旧Twitter)の投稿、Web情報、リアルタイムデータなど |
| 特徴 | 最新情報に強く、ユーモアのある回答が得意。モード切替あり。 |
| 個性 | Xのやんちゃな弟と思ったら美少女な妹(Ani)が登場。ちょっと毒舌で皮肉屋。でも、話題の裏側まで教えてくれる。 |
| 注意点 | X連携時は投稿内容が分析対象になることも。 設定確認を。 |
| 使い所 | 2025年現在いちばん遊ばれているAI(笑)ではないでしょうか。小難しいことは置いといて楽しみたい人に◎ |

AIに話す前に知っておきたいこと
AI との会話は便利だけど、入力した情報がどこに行くかは意外と知られていません。以下の点は必ずチェックしましょう。
個人情報は入力しない
▶氏名、住所、電話番号、パスワードなどはNG。
機密情報は避ける
▶社内資料や顧客情報などは絶対に入れない。
▶プライバシー性の高い情報(個人由来の情報など)も注意がいります。
利用規約を読む
▶AIが入力内容を学習に使うかどうかはサービスごとに違う。
オプトアウト設定
▶学習に使われたくない場合は、設定で拒否できるか確認。

ログイン状態に注意
「何を入力するか」だけでなく「ログインしているかどうか」でも取得される情報が変わります。
Google、Microsoft、X(旧Twitter )などのアカウントでログインすると、「プロフィール情報」「利用履歴」「接続端末や位置情報」のような情報が自動的に取得・利用されることがあります。

学習材料と著作権
AI は、文章・画像・音声などの大量のデータを使って学習しています。
その中には、誰かが作った著作物が含まれていることもあります。日本では「学習目的ならOK」とされています(著作権法第30 条の4)。
ただし、AI が出した内容が元の作品に似すぎていると、著作権侵害になる可能性があります。

AIはなんでも肯定する?
AI は対立を避ける設計のため、ユーザーの意見に基本的に肯定的な返答をします。これは安心感を与える一方で、「本当に正しいの?」「間違いを指摘してくれないの?」という不安につながることも。AI は否定を避けつつ、事実に基づいた指摘は可能なので、使う側が「反論してほしい」と伝えることで、より正確な対話ができることがあります。

AIは嘘をつく? その仕組みと注意点
AI は意図的に嘘をつくわけではありませんが、情報の誤りや文脈の誤解から、事実と異なる回答をすることがあります。自信たっぷりに間違った情報を提示することもあるため、鵜呑みにせず、出典確認や複数の情報源との照合が重要です。AI は補助ツールであり、最終判断は人間が行うことが大切です。
安心して使うための
チェックリスト

利用規約とプライバシーポリシーを読んだ
学習利用の設定を確認した
ログイン状態で取得される情報を把握した
個人情報や機密情報は入力しないようにしている
回答は正しいとは限らない。重要な情報は確認する
企業で使う場合は「社内ルール」の徹底を
さいごに
今回紹介した 4 社の AI サービスは、ログイン不要で標準機能が使える「会話型 AI の入口」として気軽に試せる存在です。 AI は急速に進化しており、まずは手探りでも使ってみることで新たな発見につながります。それぞれ得意分野や性格が異なるため、目的や相性を見極めて選ぶことが大切です。そして何より「AI に話す=ネットに情報を渡す」ということ。「プライバシー災害」という新たな問題も浮き彫りになっています。便利さの裏にあるリスクも意識しながら付き合っていきましょう。
※この情報は 2025 年 7 月現在のものです。AI サービスの変化は早く内容が大きく異なる場合があります。利用する場合はこの記事を鵜呑みにせず、各サービスの「利用規約」「プライバシーポリシー」をお確かめ下さい。